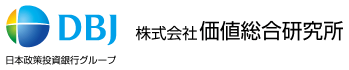CULTURE TALK カルチャー座談会
変わらない志。
社会課題を解決して社会に貢献する。
~より良い世の中にするために~

MEMBER
-

大口 寛貴
ポリシーエンジニアリング事業部
副主任研究員工学研究科環境社会基盤工学専攻修了
2023年入社 -

密原 大豪
ポリシーエンジニアリング事業部
研究員経済学部経済経営学科卒
2024年入社 -

岡村 遥
ポリシーエンジニアリング事業部
研究員農学府農学専攻修了
2023年入社 -

渡邉 駿
ポリシーエンジニアリング事業部
研究員工学研究科社会基盤環境工学専攻修了
2024年入社
SESSION 01 前職で経験したこと。価値総研への入社を決めた理由。
前職での経験を活かして、
自分が本当にやりたいことを
価値総研で実現できると思った。

-
大口
今日集まったのは、2023年から2024年にかけて入社したメンバーですが、まだ記憶に新しい入社当時のことから話を始めたいと思います。渡邉さんは、インフラ関連の会社に勤務していたと聞いています。転職のきっかけを教えてください。
-
渡邉
私は大学卒業後、鉄道会社に就職。転職直前まで、新駅建設及び駅周辺再開発の工事発注業務や、工事に関係する地権者等のステークホルダーとの調整業務を担当していました。国家的なビッグプロジェクトであり、そのやりがいは大きなものがありましたが、その仕事内容は、すでに方向性の決まったプロジェクトを推進させていくこと。社会的貢献度の高い業務ではあったものの、私は「世の中をより良くするためにはどうすれば良いか」という方向性を検討することに関心があったため転職しようと考えました。
-
密原
その際に、価値総研を選んだ理由は?どの辺りに魅力を感じたのですか?
-
渡邉
大学時代、データ分析から交通・物流や環境に関する施策を検討する研究を行っていました。リサーチ・コンサルティング業界では大学時代の経験と鉄道会社での経験の両方を活かすことができると考えました。価値総研は、採用面接の際に、具体的な業務内容やキャリアプランについて丁寧に説明していただき、自分が価値総研で働いているイメージを想像することができ、「ここで働いてみたい」と思えたことが入社を後押ししました。密原さんは?
-
密原
私は、前職でもシンクタンクに勤務しており、主に都市・交通分野の政策動向や技術動向に関するリサーチ・コンサルティング業務に従事していました。これまで馴染みのなかった領域の知見を得られることに楽しさを感じていましたが、一方でその場しのぎ的な業務遂行になっているという感覚もあり、将来的に自分自身の核となる専門分野が身に付かないのではと不安を感じるようになりました。専門分野を中心に、改めて自らのキャリアについて考え直す機会にしたいと思い、転職を決意しました。
-
岡村
同じ業界内での転職だったのですね。やはりこの仕事が好きだったのですか?
-
密原
ええ、リサーチ・コンサルティング業務自体はとても楽しく、自分に合っている仕事だと感じていたため、転職活動の際も、他の業界に転職するという選択肢はほとんど考えていませんでした。価値総研に興味を持ったのは、独自モデルを活用した唯一無二のリサーチ・コンサルティングサービスを提供していること。さらに、採用面接では、価値総研が受託する業務のスケールの大きさ、社会的意義等を伝えていただき、他のシンクタンクでは経験できない面白い業務に携われそうだと感じたことが、価値総研に入社した決め手になりましたね。岡村さんも同業他社からの転職と聞いています。
-
岡村
はい。大学院時代から環境問題を研究テーマとし、その知見を活かそうと思い環境コンサルの会社に就職。地方自治体向けに再エネ導入計画策定に向けた調査・策定業務等に携わりました。当時問題意識としてあったのが、より実行力のある計画は何かということ。そして考えたのが、脱炭素などの環境問題解決と同時に、地域活性化が達成できるような計画策定・取り組みをしたいということです。環境のためだけにお金を使うのではなく、行く行くは地域経済のためになるものであれば、理解も得やすく効果も高いと思い、それを実践できる場を考えました。環境に寄り添い、且つ地域活性化を打ち出していたのが価値総研であり、自分のやりたいことができると思い入社を決めました。大口さんもコンサルからの転職ですよね。
-
大口
ええ、大学院を出て6年間建設コンサルタントとして、主に地方自治体に向けて都市計画に関する業務を担当していました。ただ自治体の仕事は発注者至上主義のようなところがありました。自治体の意向に沿ったものがすべて適切とは限りません。たとえば、市街地拡大や企業誘致等による都市の拡散は、都市計画的には抑制的であるべきですが、自治体の意向と対立する場合もあります。私が求めたのは発注者と対等な立場で議論することであり、それが実現できる場が価値総研でした。価値総研の掲げる理念は自分の考えと完全に一致。それが入社を決めた理由です。

SESSION 02 現在取り組んでいる仕事内容は?
環境問題の解決と経済成長の実現。
「共生圏事業」が生む「Well-being」。
地方自治体の総合計画から、
「コンパクトシティ」の形成へ。

-
大口
私たち4人が所属するポリシーエンジニアリング事業部は、国や自治体の政策立案に向けたさまざまなソリューションを提供する部署。4人とも主に国や自治体に関わる業務が多いと思いますが、具体的にそれぞれどのような取り組みなのか。岡村さんからお願いします。
-
岡村
私は「地域経済循環分析」を用いた脱炭素化による地域産業への影響の分析や、地域の経済構造の向上に資する施策の方向性の提案等に携わっています。地域における環境施策を円滑に推進していくためには、環境課題と経済・社会的課題の同時解決を図る取り組みを立案することが重要です。つまり環境立案のためには地域の経済循環構造を把握する必要があり、そのツールが「地域経済循環分析」です。
-
密原
私も環境に関わる業務を担当しています。経済モデルによるマクロ経済分析を担当しており、政府が推進する環境対策等の政策が、我が国の経済に与える影響等の分析を行っています。岡村さんの脱炭素の取り組みが非常に興味深いのですが、どのような取り組みか教えてください。
-
岡村
脱炭素に代表される環境問題の解決や対策を実施する上で、近年世界的に注目されているのが「Just Transition=公正な移行」という概念です。脱炭素社会への移行のプロセスでは、多くの産業・社会に影響をもたらすことが想定されます。地球温暖化防止の取り組みがもたらすことの多くは、プラスの面が強調されますが、一方で失業や廃業、産業構造の転換による地域衰退というマイナスのリスクも考えられます。脱炭素社会の実現によって、労働者や地域が取り残されることなく公正に持続可能な社会に移行していくことが求められています。日本においてどのような「Just Transition」が最適か、さまざまなアプローチで検討を開始しています。密原さんの取り組みは経済成長と環境対策の両立を目指すものですか?
-
密原
ええ、一般的に経済と環境はトレードオフの関係と言われる中、それらをいかにして両立していくか。また、経済だけでなく、環境対策は社会に対しても様々な影響を与えることが考えられます。環境対策が経済や社会に与える影響を可視化し、政策が本当にターゲットとすべきなのはどこか、総合的に判断することが求められます。実際には、経済モデル等のモデルを用いて計算を行い、計算結果を踏まえて課題の分析やソリューションの検討等を行います。その上で、分析結果を資料に整理し、打ち合わせの場でお客さまにご説明する、といった流れになります。渡邉さんは、最近新たな課題に取り組んでいますよね。
-
渡邉
ええ、入社後、日本を牽引してきた産業が今後発展していく見込みなのか、もしくは衰退してく見込みなのか、またそれが環境政策や日本経済、地域経済にどのような影響を与えるか等のリサーチを行っていました。現在は東北地方のある地方自治体の総合計画策定の支援業務を担当しています。総合計画は地方自治体の最上位にあたる計画であり、将来に向けてまちはどうあるべきか、都市計画や産業、人口減少、貧困格差、社会的差別等々の課題を見据えて、それらを解決しまちの持続的発展を目指す取り組みを検討しています。たとえば、担当している自治体はエネルギー産業に依存している傾向がありますが、伝統的に第一次産業にも強みを持っています。それら貴重なアセットを地域経済の発展やまちづくりに活かしていけないかなど、多角的視点で取り組んでいます。
-
岡村
それは、環境省が発信している「共生圏事業」とも関連してくると思いますね。私自身も関わっている取り組みですが、地域資源を活用して環境・経済・社会の統合的向上を実現する事業を生み出し続けるとともに、地域の個性を活かして地域同士で支え合うネットワークを形成していくという「自立・分散型社会」を示す考え方。具体的には、「共生圏事業」を広めていくために、今までやってきた効果を計測する取り組みに着手しました。現在は効果を調べるための分析手法の検討を進めています。たとえば、ある地域で行った「木質バイオマス発電事業」が、経済をはじめどのような効果を地域にもたらしたのか、明確に数値化することで、「共生圏事業」、そして「Well-being」の実現へ結び付けていきたいと考えています。
-
大口
渡邉さんが取り組んでいる地方自治体の総合計画の検討には、私もプロジェクト全体の工程管理をはじめとしたマネジメント担当として関わっています。それだけでなく、私自身が以前から取り組んでいる「コンパクトシティ」とも密接に関わるプロジェクト。コンパクトシティは、コンパクトという言葉の通り「小さくまとまったまち」を目指すものです。住まいや公共交通、商業・医療・福祉施設などを集約し、郊外に居住地が拡散することを抑えたサステナブルな都市構造といえます。しかし自治体の一部は、人口流入への期待や企業誘致による雇用確保等の意図から、郊外へ都市の拡散を志向する傾向にあり、それを止めるのは困難な状況にあります。それを突破するロジックを組み立て、エビデンスを明確にするのが私のミッション。そのための切り口の一つが環境です。たとえば、都市が拡散すると自動車移動が増えCO₂排出が増大する、あるいは無計画な市街地拡散が、自然破壊や災害時の被害拡大などを生むなど、市街地拡散抑制の必要性を理解・納得してもらうロジックを組み立てています。

SESSION 03 やりがい、そして価値総研のカルチャー
前例がない業務に
チャレンジしていく醍醐味。
社会問題を自分事として考え、
徹底して最適解を追求する。

-
岡村
私たちの業務の多くがそうだと思いますが、まだ誰も試算・分析していないことにチャレンジしていくことは、難しいところですが、同時にやりがいでもありますね。正解がない中で、情報を収集し、条件設定を考え、最適解を見出していく過程に面白さを感じています。具体的な施策に反映されて成果が生まれたという経験は、まだありませんが、施策を考えていく方向性をお客さまと検討し、また検討の過程で新たな発見や気づきがあるときもやりがいを感じます。
-
大口
そうですね。私も実感するのが、前例がほとんどない業務であること。したがってロジックの組み立てと一言で言っても、一朝一夕でできることではない。ただ岡村さんと同様に、その困難な壁にチャレンジしていること自体にやりがいを感じています。
-
密原
価値総研では、高度な独自モデルを用いた分析を強みとしていますよね。一方、これらは複雑なモデルであり、お客さまに理解いただくのが難しいと感じる場面が多々あります。モデルを使う側としてはどうしても、モデルの理論や計算過程を詳しく説明したくなりますが、それよりも、モデルが現実世界のどのような事象を表現しているか、計算結果から得られる示唆は何か、といった点を分かりやすくお伝えすることを心がけています。そして、導出した結果についてお客さまに納得いただき、その結果を政策等に活用いただく際にやりがいを感じますね。価値総研は小さい会社ですが、スケールの大きい業務をいくつも受託しており、業務を通じて社会への貢献を実感しますね。
-
渡邉
価値総研の仕事の特徴に一人が一つの専門分野を担当するわけではなく、複数の分野を担当するということがあると思います。そのため、多角的な視点から物事を考えられるようになることが、仕事のやりがいの一つだと感じています。また、自分の行った調査や分析などから、お客さまが新たな問題意識や気づきを得られ、業務内容を評価してくださったときなど、達成感を感じますね。
-
密原
入社して感じるのは、社会を良くするためにはどうすれば良いかを真剣に考えている人が多いということ。一般の企業に勤める多くの人も社会貢献の意識は持っていると思いますが、価値総研のメンバーはその熱量が高い。社会にとってそれが良いことなのかどうか、徹底して考えるのが価値総研の人。お客さまと議論することを厭わない姿勢にもそれは感じます。
-
渡邉
世の中の社会問題を自分ごととして考え、業務を通して世の中の社会問題をどのように解決していくかを意識して仕事をしている人が多いと思いますね。みんな、会社としてどうすべきか、お客さまのためにはどうすべきか、世の中のためにはどうすべきかといった広い視野をもって考え判断し、仕事を進めていると感じますね。
-
大口
同感です。社会の発展を目指し、誰もが住みよいまち・環境をつくっていくという使命感を持った人が多いと感じますね。また個々人の専門性が高いのも価値総研の特徴だと思います。わからないことは、誰かに聞けば答えが見つかりますから。
-
岡村
そうですね。みなさん知識が豊富で常に向上心があり、お客さまの課題解決のためにより質の高い提案をする姿勢を崩さない。加えて、いい意味でみなさん個性的。個々人が自分の得意なことを活かして仕事をしているように感じます。キャリア採用のメンバーが多く、バッググラウンドの異なる人が集まっている多様性も価値総研の特徴の一つだと思います。
-
大口
ええ、同感です。多様な人と交わる環境が成長を促していると思いますね。また多彩な研修制度に加えて、自己研鑽のための書籍購入の支援など、意欲的に学べる環境が整っていますし、業務それ自体が成長を後押ししていると感じますね。
-
岡村
私もそう思います。業務に必要なことはチャレンジさせてくれる環境です。入社数ヶ月で海外出張も経験しました。先日は、アゼルバイジャンで開催された「COP29」にも参加しました。他にも営業への同行、業務実地地域に赴くなど、さまざまな経験ができるのが価値総研。そうした環境が成長の力になっていると思います。
-
密原
他のシンクタンクと比較して、後輩社員に対して熱心に指導してくださる先輩社員が多いように感じます。若手社員の成長を、組織的にサポートしていくような制度と風土が揃っている会社。社内の打合せや勉強会では、社会課題に対する分析結果等について仲間と議論を深める機会が度々あり、お互いの成長に繋がっていると思います。社員の成長への意識が高いと感じますね。
-
大口
そうですね。日々の業務が成長の場。経験豊富なメンバーからのフォロー、チームメンバーでの議論等、周囲の環境が成長を促していると思いますね。

SESSION 04 今後の目標と求職者へのメッセージ
より多くの人が幸せに暮らせる、
まち・社会づくりに貢献する。
社会の役に立ちたいという想いを
実現できるのが価値総研。

-
密原
まずは私が担当する経済モデルによるマクロ経済分析において、業界内で一番の専門性を身に付けることが目標です。その上で、身に付けた専門性を価値総研での政策コンサルティング業務を通じて発揮し、より多くの人が幸せに暮らせる社会づくりに貢献したいと考えています。
-
渡邉
中央省庁の大きなプロジェクトに関係する業務に携わり、社会に大きく貢献したいと考えています。そのためにも日々の業務や自己研鑽から知識と技能を高めていきたいと思っています。お客さまの課題解決と社会の発展のために、少しでもお役に立てるようになりたいですね。
-
大口
価値総研の特徴に「ひとりで総合シンクタンク」というのがあります。つまり個人が複数の専門領域を持つことであり、そこに惹かれたのも入社理由の一つでした。さまざまな業務を経験して知見を深め、「ひとりで総合シンクタンク」になることが目標です。
-
岡村
私は大学や前職では環境問題を中心に取り扱ってきました。価値総研に入社して環境+経済の取り組みが始まっています。したがって経済への知見を深めることが目下の課題であり、それによってよりよい提案ができるようになりたいと思っています。経済のみならず、環境+α的な立ち位置で、人と人を繋げる触媒のような存在になりたいと思っています。
-
大口
最後に求職者へのメッセージを一言伝えたいと思います。価値総研は業務を通じて総合的な専門性を習得し、発揮できる場です。今の社会に課題意識を持っている人、業務を通じて課題解決に取り組み、社会の発展を一緒に目指しましょう。
-
密原
価値総研は小さな会社ですが、高度な独自モデルを複数有し、スケールの大きな業務をいくつも受注している、とても珍しいシンクタンクです。データをもって社会の課題を分析し、社会をより良くするための解決策を考えることに面白さを感じる人であれば、価値総研での業務は非常に楽しいものになるはず。今回の座談会で興味をもった方は、ぜひ応募していただければと思いますね。
-
渡邉
価値総研の業務は社会貢献度が非常に高く、業務を通じて自身も大きく成長することができます。入社を検討されている方がいらっしゃいましたら是非一度、当社にアプローチしていただければと思っています。
-
岡村
社会の役に立ちたいと思っている人、そして新しいことへのチャレンジを楽しめる人であれば、価値総研に向いていると思います。ぜひ、一緒に働きましょう。